コロナはインフルの類なんて寝言を言うな!
2020年12月28日 16:47
301名の医師が参考になったと回答
無料でいますぐ会員登録を行う
【医師限定】
初回登録で500円分のポイントをもれなく進呈!
(7月末迄/過去ご登録のある方を除く)
- ・ ご利用無料、14.5万人の医師が利用
- ・ 医学・医療の最新ニュースを毎日お届け
- ・ ギフト券に交換可能なポイントプログラム
- ・ 独自の特集・連載、学会レポートなど充実のコンテンツ
トップ » 連載・特集 » ドクターズアイ 岩田健太郎(感染症) » コロナはインフルの類なんて寝言を言うな!
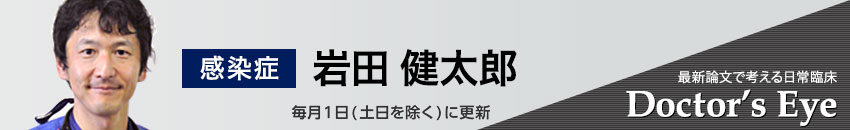 ドクターズアイ 岩田健太郎(感染症)
ドクターズアイ 岩田健太郎(感染症)
2020年12月28日 16:47
301名の医師が参考になったと回答
初回登録で500円分のポイントをもれなく進呈!
(7月末迄/過去ご登録のある方を除く)
トップ » 連載・特集 » ドクターズアイ 岩田健太郎(感染症) » コロナはインフルの類なんて寝言を言うな!